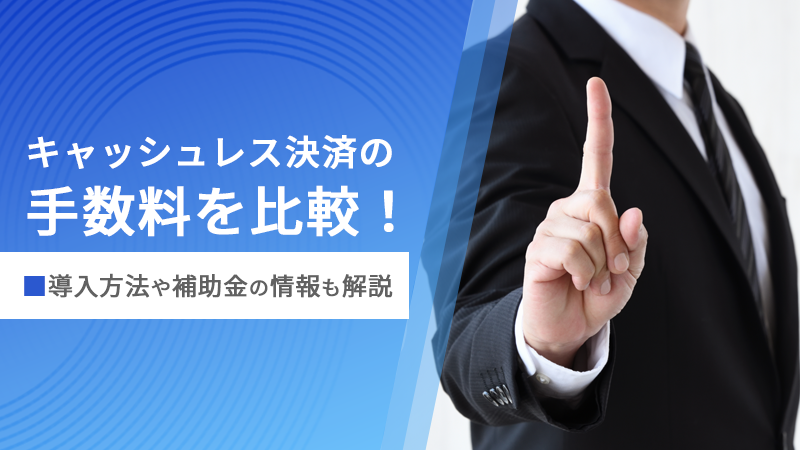
キャッシュレス決済は、もはや多くの顧客が「当たり前」と考える支払い手段になりつつあります。
しかし、店舗側にとっては「手数料がどれくらいかかるのか」「本当に費用に見合った効果があるのか」といった不安を抱えるケースも少なくありません。
この記事では、キャッシュレス決済の手数料の仕組みをはじめ、種類ごとの手数料相場や導入方法を解説します。導入により期待できるメリットや補助金の活用方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
キャッシュレス決済の手数料とは?なぜ発生する?
キャッシュレス決済の手数料とは、店舗がキャッシュレスでの支払いを受け取る際に、売上金の一部を決済サービス提供会社に支払う費用です。
とくにクレジットカード決済では、顧客が支払う前にカード会社が代金を一時的に立て替えているという「信用取引」の性質があります。このリスクを負う代わりに、カード会社は加盟店から手数料を受け取っています。
手数料率は売上の数%が相場であり、決済手段や店舗の規模、業種によって1〜10%と大きく異なりますが、3%台の割合が高いです。
たとえば、1,000円の商品をキャッシュレスで販売した場合、手数料が3%であれば30円が差し引かれ、店舗に入金されるのは970円となります。
参考:経済産業庁ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/cashless_sub/questionnaire_result.pdf)
決済手数料を顧客に上乗せ請求することは規約違反
キャッシュレス決済の手数料は店舗が負担すべき経費であり、顧客に上乗せして請求することは、多くの決済サービスの加盟店規約で禁止されています。
上乗せ請求が禁止される背景には、価格の透明性の確保、キャッシュレス社会の健全な推進に加え、消費者保護といった目的があります。利用者は提示された価格で商品やサービスを購入する権利があり、決済方法によって差別されるべきではないためです。
ルールに違反した場合、決済サービスの利用停止や加盟店契約の解除など、厳しいペナルティが科される可能性があります。
出典:PayPayウェブサイト(https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/)
出典:楽天ウェブサイト(https://pay.rakuten.co.jp/business/policy)
【比較】キャッシュレス決済の種類ごとの手数料相場
キャッシュレス決済には複数の種類があり、それぞれ手数料率は異なります。
下表は、主な決済手段ごとの手数料相場を比較したものです。
| 決済手段 | 主な提供事業者 | 手数料相場 |
|---|---|---|
| クレジットカード | ・VISA・Mastercard・JCB など | 約1~7% |
| 電子マネー | ・Suica・PASMO・楽天Edy など | 約3~4% |
| QRコード | ・PayPay・楽天ペイ・LINE Pay など | 約1~3% |
| キャリア決済 | ・d払い・au PAY・ソフトバンクまとめて支払い など | 約5~10% |
それぞれを詳しく見ていきましょう。
クレジットカード決済
クレジットカード決済では、カード会社が顧客の代金を一時的に立て替える「信用取引」が行われます。
この信用供与に加え、与信審査による貸し倒れリスクの負担、不正利用時の補償などにかかるコストの対価として、加盟店から手数料が支払われます。そのため、クレジットカード決済の手数料は、導入する店舗の規模や業種によって差があります。
個人経営など小規模事業者では、手数料率が高く設定されている場合があります。一方で、取引量が大きい事業者では、1%前後の低料率が適用されるケースも見られます。
ただし、中小事業者向けに1%台の低料率プランを提供する決済サービスもあるため、複数のプランを比較し、自店舗に合ったものを選ぶことが重要です。
電子マネー決済
電子マネー決済の手数料相場は、売上の約3〜4%です。
たとえば、1,000円の商品を販売した場合、30〜40円程度が事業者の負担となります。
来店客のニーズや利用頻度を踏まえ、導入するかどうかを判断するとよいでしょう。
QRコード決済
QRコード決済の手数料は、一般的に1〜3%程度とされており、キャッシュレス決済のなかでも比較的コストを抑えられるのが特徴です。
とくに、若年層を中心にQRコード決済の利用が進んでおり、利用頻度の高い軽飲食店などではニーズが高まっています。
1,000円の会計でも30円前後の手数料負担で済むことから、小規模店舗にとっても導入のハードルが低い選択肢といえるでしょう。
出典:NIRA総合研究開発機構ウェブサイト(https://nira.or.jp/paper/research-report/2023/212309.html)
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。
キャッシュレス決済運用で手数料以外に必要な費用
ここでは、キャッシュレス決済運用において発生する「手数料以外の費用」について紹介します。
初期費用
キャッシュレス決済を導入する際、初期費用が発生する場合があります。
具体的には、クレジットカードや電子マネーの読み取りに必要な決済端末の購入費用や設置費用などが該当します。
サービスによっては、端末を無償で貸与してくれるところもありますが、購入が必要なケースでは数千円〜数万円程度の初期投資が求められることもあります。
ただし、近年では導入を促進する目的で、初期費用が無料または割引になるプランを提供する事業者も増えているため、コストを抑えたスタートも可能です。
サービスの月額利用料金
キャッシュレス決済を利用する際、毎月発生する「月額利用料金」が必要になる場合があります。
月額利用料はサービスの利用にともなう固定費となるため、事前に内容と金額をしっかり確認しておくことが大切です。
振込手数料
キャッシュレス決済で得た売上を銀行口座へ入金する際、振込手数料がかかる場合があります。
手数料の金額や発生条件は、利用するサービスや契約内容によって異なりますが、一般的には1回あたり数百円程度です。
しかし、振込の頻度が高いと、その分トータルの負担も大きくなります。
なかには、特定の銀行口座を指定すれば手数料が無料になるサービスもあるため、導入前に条件を確認しておくとよいでしょう。
解約手数料・違約金
キャッシュレス決済サービスを途中で解約する場合、契約内容によっては手数料や違約金が発生する可能性があります。
たとえば、月額料金制やサブスクリプション型のサービスでは、最低契約期間が定められており、その期間内に解約すると解約手数料が発生することがあります。
また、決済端末をレンタルしている場合、返却時に故障や破損があると、違約金を請求される可能性もあるため注意が必要です。
その他費用
キャッシュレス決済を導入する際は、手数料や端末代以外にも見落としがちなコストがあります。
代表的なのが、インターネット環境の整備です。キャッシュレス決済はインターネット通信が前提となるため、Wi-Fiや有線回線が未整備の場合は、新たに通信環境を整える必要があります。
また、QRコード印刷用のプリンターや、決済端末と連携するPOSレジ・レシートプリンターなど、周辺機器の購入・レンタル費用も発生する可能性があります。
細かな費用も含めて事前に予算を立てておけば、予想外の出費を避け、スムーズに導入・運用を進められるでしょう。
キャッシュレス決済の手数料に消費税はかかる?
ここでは、3つの主要な決済方法ごとに、手数料に対する消費税の取り扱いを紹介します。
クレジットカード決済の場合
クレジットカードの決済手数料は、原則として消費税の課税対象にはなりません。
なぜなら、クレジットカード会社が消費者に代わって店舗に代金を立て替える際、店舗の売掛金、つまり将来受け取るべきお金を買い取ることとみなされるためです。
ただし、カード会社ではなく決済代行会社を通じてクレジット決済を利用している場合は注意が必要です。
代行会社が提供するサービス内容によっては、一部の手数料に消費税が課税される可能性があります。
そのため、請求明細や契約書に記載された費用の内訳を確認し、消費税の取り扱いを事前に把握しておくことが大切です。
電子マネーの場合
電子マネーによる決済手数料の消費税の扱いは、利用される電子マネーの種類によって異なります。
代表的な決済手段は、前払い(プリペイド)、後払い(ポストペイ)、即時引き落とし(デビット)の3種類です。
プリペイド型の電子マネーは、事前にチャージした金額から支払いが行われるため、決済手数料は消費税の課税対象です。一方、ポストペイやデビットはクレジットカードと同じ性質をもつため非課税となります。
電子マネーの種類と利用形態によって税区分が異なるため、契約している決済サービスの仕様書や明細書を確認し、正確に把握しておくことが重要です。
QRコード決済の場合
QRコード決済にかかる手数料の消費税の扱いは、利用者が実際に選択する支払い方法によって異なります。
たとえば、クレジットカードを紐付けて後払いする場合、手数料は非課税です。
一方、事前にチャージした残高や銀行口座からの即時引き落とし、またはポイントを利用して支払う場合は、サービスを提供したことへの対価としての手数料とみなされ、課税対象となります。
キャッシュレス決済を導入するメリット
キャッシュレス決済を導入する際、どうしても気になるのが「決済手数料」というコストです。
とくに中小規模の店舗では「毎回の売上から一定割合が差し引かれるのは痛手だ」と感じる方も多いでしょう。
しかし、そのコストを上回るメリットがあるのも事実です。
ここでは、キャッシュレス決済を導入することで得られる主なメリットを紹介します。
会計業務の効率がアップする
キャッシュレス決済における最大のメリットが、会計処理の効率化です。
現金の受け渡しやお釣りの計算が不要になるため、1件あたりの会計時間が短縮され、レジ対応がスムーズになるでしょう。
実際、経済産業省の調査によれば、キャッシュレス決済を導入した店舗ではレジ対応時間が約35%短縮されたという結果が出ています。
スピーディな会計は、ピークタイムの混雑緩和や顧客満足度の向上にもつながります。来店客の回転が早くなることで、売上の増加にも好影響を与えるでしょう。
出典:経済産業省ウェブサイト
(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/image_pdf_movie/leaflet_tenpo.pdf)
現金管理のセキュリティが向上する
キャッシュレス化が進むことで、店舗内の現金取扱量が減少します。その結果、盗難や紛失といったトラブルのリスクが軽減され、管理業務の負担も大きく減ります。
とくに閉店後の売上金集計や金庫の管理、銀行への入金作業といった業務にかかる時間や心理的ストレスは、現金を取り扱う限り避けられません。
深夜営業の店舗や人どおりの少ない立地では、現金を持たない営業体制が防犯対策として大きな効果を発揮するでしょう。
端末ひとつでさまざまな決済方法に対応できる
近年のキャッシュレス端末は、クレジットカード、QRコード決済、電子マネーなど、複数の支払い方法に対応できる多機能型が一般的です。
端末を1台設置するだけで、幅広い決済手段に対応できるのは、店舗にとって大きなメリットといえるでしょう。
顧客データを分析に活用できる
キャッシュレス決済をPOSシステムと連携させると、来店客の購買履歴や利用頻度などのデータを蓄積できます。
これにより、どの商品がどの時間帯に売れているか、リピーターが多い曜日や時間帯はいつかなど、店舗運営に役立つ情報を視覚的に把握できるようになります。
単なる勘や経験に頼るのではなく、数値にもとづいたマーケティングが実現できるでしょう。
客単価アップが期待できる
キャッシュレス決済を導入すると、1人あたりの購入金額が増える傾向があります。
なぜなら、現金とは異なり、所持金を気にせず支払いができるため、追加の商品を購入したり、高単価の商品を選んだりしやすくなるからです。
さらに、キャッシュレス決済に対応していれば、日本人だけでなく訪日外国人にも利用してもらいやすくなります。
現金を持たずに買い物をしたい観光客にとって、対応店舗は安心して立ち寄れる存在となり、売上拡大のチャンスにもつながるでしょう。
【手数料以外】キャッシュレス決済導入のデメリット
ここでは、導入前に押さえておきたい3つのデメリットを紹介します。
トラブル時に利用できなくなる可能性がある
キャッシュレス決済は便利な一方で、システム障害や通信トラブル、端末の故障が発生すると決済ができなくなるリスクがあります。
とくに混雑時にトラブルが起こると、レジ対応が遅れ、待たされる顧客の不満が高まりやすくなります。その結果、店舗への印象や信頼に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
こうした非常時に備えて、現金での支払いをすぐに受け付けられる体制を整えておくことが重要です。
同時に、予備の決済端末を用意したり、通信障害に備えてバックアップ回線を導入することで、トラブル時の対応力が高まります。
売上金が入金されるまでに時間がかかる
キャッシュレス決済では、売上金が現金のように即日入金されるわけではありません。
入金の遅れは、仕入れなど現金支出の多い店舗にとって資金繰りの負担となる可能性があります。
そのため、導入前に入金スケジュールを確認し、自店舗の資金計画に適したサービスを選ぶことが重要です。
スタッフの教育が必要になる
キャッシュレス決済を導入すると、スタッフは新しい端末の操作に慣れる必要があります。
クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、決済方法によって操作が異なるため、最初は戸惑う場面もあるでしょう。
また、操作に不慣れな顧客への説明や、トラブル時の対応も求められるため、スタッフには基本的なサポート力も必要です。
スムーズな運用のためには、わかりやすいマニュアルを用意し、導入時に研修やレクチャーを行うなど、現場で迷わない体制づくりを整えておくことが大切です。
初期段階では教育コストがかかりますが、習熟すれば業務の効率化につながります。
キャッシュレス決済の導入方法
キャッシュレス決済の導入方法は大きく分けて、以下の2つです。
- キャッシュレス決済サービス会社と直接契約する
- 決済代行会社を通して契約する
店舗の規模や業種、扱いたい決済手段の数によって、適した導入方法は異なります。
それぞれの方法の特徴を把握したうえで、自店舗に合った導入プランを検討しましょう。
キャッシュレス決済サービス会社と直接契約する
キャッシュレス決済を直接サービス会社と契約することで、仲介手数料を抑えられ、導入コストを軽減できます。
ただし、複数の決済事業者と個別に契約や審査手続きを行う必要があるため、導入準備に時間と手間がかかる点に注意が必要です。
また、決済手数料や入金スケジュールが事業者ごとに異なるため、費用管理や経理処理が複雑になる可能性があります。
手間を踏まえて、自社に合った導入方法かどうかを慎重に判断することが重要です。
決済代行会社と契約する
多様な決済方法を一括して導入・管理したい場合は、決済代行会社と契約する方法が適しています。
決済代行会社は、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済など、複数の決済サービスを一括で導入できる窓口として機能します。
個別に契約・審査を行う手間が省けるだけでなく、売上や手数料の管理、トラブル対応までまとめて任せられるため、導入後の業務負担も大幅に軽減されるでしょう。
また、システムサポートも代行会社が対応してくれるため、専門知識がなくても安心して運用できます。
キャッシュレス決済サービスの選び方
ここでは、キャッシュレス決済サービスを比較検討するうえで押さえておきたい3つの選定基準を紹介します。
顧客層に合っているか
キャッシュレス決済を導入する際は、来店客の年齢層やライフスタイルに合わせて、最適な決済手段を選ぶことが大切です。
たとえば、学生や若年層が多い店舗では、スマートフォンで簡単に支払いができるQRコード決済や電子マネーが人気です。一方、家族連れやビジネスパーソンの利用が多い店舗では、比較的高額な決済が発生しやすいため、クレジットカードの導入を検討しましょう。
また、外国人観光客が多い地域では、交通系ICカードや海外ブランド対応の端末があると、利便性が高まります。
ターゲット層の利用傾向に合わせて決済手段を選ぶことで、導入後すぐに顧客ニーズに応えられるため、スムーズな運用につながります。
出典:NIRA総合研究開発機構ウェブサイト(https://nira.or.jp/paper/research-report/2023/212309.html)
多くの人に利用されているか
キャッシュレス決済を導入するなら、できるだけ多くの人が日常的に使っている決済ブランドに対応しているサービスを選ぶことが大切です。
たとえば、日本国内で楽天カードは幅広い年代が利用しています。また、PayPayや交通系ICカードも高い普及率を誇ります。
これらの主要ブランドに対応しているかを確認することで、顧客の「使いたいのに使えない」という機会損失を防げるでしょう。
出典:MMDLabo株式会社ウェブサイト(https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2413.html)
入金サイクルは短いか
キャッシュレス決済サービスを選ぶうえで、見落としがちなのが「入金サイクル」です。
売上金が入金されるまでの期間が長いと、資金繰りに支障をきたすおそれがあります。
日々の運転資金が限られている中小店舗では、現金のように即時で使えないことが負担になる可能性もあります。
そのため、最短で翌日入金や週に複数回入金に対応しているサービスを選ぶことで、キャッシュレス導入後も安定した資金繰りを維持しやすくなるでしょう。
キャッシュレス決済の導入には補助金を活用しよう
キャッシュレス決済の導入は、補助金を上手に活用することで費用負担を抑え、よりスムーズに始められます。
まずは、自社が所在する地域でどのような補助制度が実施されているかを調べましょう。
【全国】キャッシュレス決済導入に使える補助金
キャッシュレス決済を導入する際には、国が提供する以下の補助金を活用することで、初期費用の負担を大きく抑えることが可能です。
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 業務改善助成金
- 全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業
なかでも「IT導入補助金」は、中小企業や個人事業者が業務効率化・デジタル化を進めるための代表的な支援制度です。
たとえば「インボイス枠」では、インボイス制度に対応する会計・受発注・決済ソフトとともに、POSレジ・タブレットなどの導入をまとめて支援してくれます。
PCやハードウェアは最大2分の1まで補助され、レジ機器は最大20万円、PCやタブレットは最大10万円の補助が受けられます。
補助制度をうまく活用することで、コストを抑えながらキャッシュレス化を実現できるでしょう。
出典:中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it_summary.pdf)
出典:中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/jizoku/)
出典:中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2025/250725kobo.html)
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)
出典:観光庁ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/page/content/001760290.pdf)
【地域別】キャッシュレス決済導入に使える補助金
キャッシュレス決済端末の導入にあたっては、地域によって自治体が独自の補助制度を設けている場合があります。
東京都北区では「新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金」を実施しており、店舗に導入するキャッシュレス端末について、費用の全額(上限10万円) を補助しています。
また、自動釣銭機などの決済機器を新紙幣対応やキャッシュレス対応機器に改修または買い替えする際は、機器1台あたり最大50万円まで(対象経費の3分の2) が補助対象です。ただし、通信料およびキャッシュレス決済手数料は補助対象外となります。
補助対象となる職種や機器の条件は自治体ごとに異なるため、自社の所在地でどのような支援制度が利用できるか、早めに確認しておくことが大切です。
出典:東京都北区ウェブサイト(https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011327/1011346/1017612.html)
まとめ
キャッシュレス決済は、単なる支払い手段にとどまらず、業務効率の向上や売上アップ、顧客満足度向上に貢献する経営ツールです。
導入には一定のコストがかかるものの、長期的には十分にリターンが期待でき、現金対応では見えにくかった課題の発見や改善にもつながるでしょう。
株式会社SCOREが提供する「スコア後払い」は、お客様が商品を受け取った後にコンビニ・郵便局で代金をお支払いいただける決済サービスです。
弊社がまず購入店へ代金を精算し、その後、お客様へ払込票を送付いたします。お客様は商品を確認のうえ、コンビニ・郵便局にて代金を弊社にお支払いいただく流れとなります。
未回収リスクを負うことなく後払い決済を提供できるため、販売機会を拡大しながらも安定した運用を実現できます。
売上を逃さない決済設計をお考えの方は、スコア後払いの導入をぜひご検討ください。




