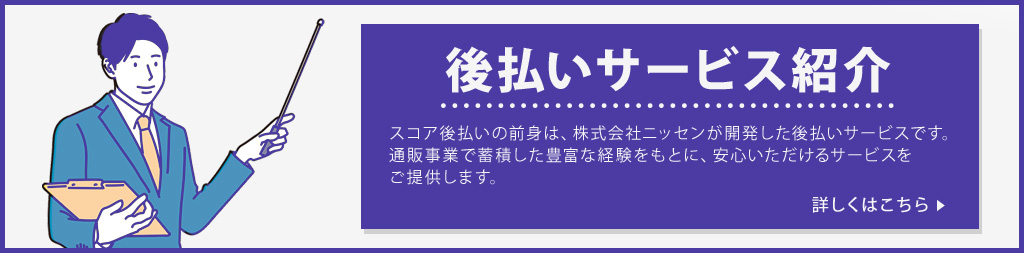定期通販やサブスクリプション事業では、新規顧客の獲得コストが年々上昇しています。広告を出しても利益が伸びず、単発購入で終わってしまうなど、課題を抱える方も多いのではないでしょうか。
そこで重要になるのが「LTV(顧客生涯価値)」という考え方です。LTVを高めることで、新規顧客に依存せず、既存顧客との関係を軸にした安定した収益構造を築くことができます。
本記事では、LTVの基本的な仕組みや計算方法、さらに定期通販で実践できる12の具体的な施策を解説します。
そもそもLTVとは?
LTVは「Life Time Value(ライフタイムバリュー)」の略で、日本語では「顧客生涯価値」と呼ばれます。これは、一人の顧客が企業と取引を開始してから終了するまでの間に、どれだけの利益をもたらすかを示す指標です。
たとえば、健康食品を毎月5,000円で3年間継続購入した場合、LTVは18万円(5,000円×36か月)となります。一方で、初回購入のみで解約した場合のLTVは5,000円にとどまります。
このように、LTVは顧客との関係をどれだけ長く深く築けているかを数値で把握できる重要な指標です。
LTVが重要視される背景
近年、LTVが注目されるようになった背景には、ビジネス環境の大きな変化があります。
とくに、広告費の高騰や競合の増加によって、新規顧客を獲得する難易度が上がっていることが大きな要因です。
新規顧客獲得の難易度が高まっている
日本の市場では、すでに多くの企業が同じ分野に参入し、商品やサービスが行き渡っています。その結果、新たに顧客を増やすことが難しくなり、競合の数は増え続けています。加えて、広告費や営業コストも上昇しており、新規顧客を獲得するハードルは年々高まっています。
マーケティングの世界では「1:5の法則」が知られており、新規顧客の獲得には既存顧客の維持よりも約5倍のコストがかかるといわれます。
このような状況では、新規顧客の獲得だけに注力するのではなく、既存顧客との関係を深めてLTVを高めることが、持続的な成長と安定した収益の実現につながります。
One to Oneマーケティングが主流となった
インターネットの普及により、企業は顧客一人ひとりの行動データや購買履歴を詳細に把握できるようになりました。
これにより、従来のように不特定多数へ同じ情報を発信する手法から、個々のニーズに合わせて最適な提案を行う「One to Oneマーケティング」へとシフトする企業が増えています。
こうした取り組みを成果につなげるには、どの顧客に重点的にアプローチすべきかを見極めることが重要です。LTVはその判断の指標となり、価値の高い顧客に的確にリソースを投じることで、マーケティングの効率と成果を最大化できます。
サブスクリプションサービスが増えている
近年、定額料金で商品やサービスを提供する「サブスクリプションモデル」が急速に普及しています。動画・音楽配信をはじめ、健康食品や化粧品の定期購入、さらには家具や自動車など、あらゆる業界に広がりを見せています。
このモデルでは、顧客がどれだけ長く契約を継続するかが収益の大きなポイントとなります。そのため、顧客との関係を長期的に育み、LTVを最大化することが、事業成長の鍵を握ります。
定期通販ではとくにLTVが重要!
定期通販はサブスクリプション型のビジネスであり、LTVと相性がよい仕組みです。
健康食品や化粧品などの消耗品では、顧客が使い続けることで自然にリピート購入が発生します。
初回購入時には、広告費やキャンペーン費用などのコストがかかるため、単体では利益が出にくいケースが一般的です。しかし、継続して購入してもらうことでコストを回収し、利益を積み上げることができます。
そのため、定期通販では「新規顧客をどれだけ獲得したか」よりも「既存顧客がどれだけ長く購入を続けてくれるか」が重要です。
LTVはこの「継続率」を数値で可視化できる指標であり、事業の安定成長を支える中核的な指標といえます。
【種類別】LTVの計算方法
LTVの計算方法はひとつではありません。
業種やビジネスモデル、さらに分析の目的によって、最適な計算式は異なります。
自社のビジネス構造に合った計算方法を選び、LTVを正確に把握することが、効果的なマーケティング施策を立てるために大切です。
業種・業界を問わず使える計算式
まずは、最も基本的で汎用性の高いLTVの計算式を紹介します。この方法は業種や業界を問わず、さまざまなビジネスで活用できるシンプルな計算式です。
顧客ごとのLTVを算出する式
顧客一人ひとりの購買データをもとに算出する方法が、最も精度の高いLTVの計算です。
LTV=平均購入単価×収益率×購買頻度×継続購買期間
各要素の意味は次のとおりです。
平均購入単価は1回あたりの平均支払額、収益率は売上に対する粗利益の割合、購買頻度は一定期間の購入回数、継続購買期間は取引の継続年数を示します。
たとえば、平均購入単価5,000円、収益率40%、年間購買頻度12回、継続期間3年の場合、
5,000円×40%×12回×3年=72,000円となります。
つまり、この顧客から3年間で72,000円の利益が得られる計算になります。
全体のLTVを荒く算出する式
個別の顧客データを追うのが難しい場合は、事業全体の傾向を把握するために簡易的な計算式を使う方法があります。
LTV=(売上高−売上原価)÷購入者数
この式では、一定期間の総利益を購入者数で割り、顧客一人あたりの平均的なLTVを求めます。手軽に全体像をつかめますが、顧客ごとの違いや時期による変化までは反映しにくい点に注意が必要です。
定期通販の商材の計算式
定期通販ビジネスでは、商品の特性や販売形態に合わせて、より実態に即した計算方法を用いることが重要です。定期通販では主に2つの計算方法が使われます。
商品全体のLTV
商品全体の傾向を把握したいときは、次の式を使います。
LTV=(売上高−売上原価)÷購入者数
先ほど紹介した簡易式と同じ計算方法ですが、定期通販では一定期間(たとえば1年間)の売上・原価・購入者数をもとに算出します。
商材ごとのLTV
商材ごとのLTVをより正確に把握したい場合は、次の式を使います。
LTV=(初回単価×初月購入件数+2〜n回目の単価×初月購入者の2〜n回目における残存者数)÷初月購入人数
少し複雑ですが、定期通販の実態を反映した実用的な計算方法です。
たとえば、健康食品を初回1,980円、2回目以降4,980円で販売し、初回購入者100人のうち2か月目に80人、3か月目に70人、4か月目に65人が継続した場合、LTVは〔1,980円×100人+4,980円×(80+70+65)〕÷100人=約12,687円となります。
つまり、1人あたり4か月で平均約12,687円の売上が見込めるということです。
初回割引や継続率の変化を反映できるため、定期通販ではこの方法でより現実的なLTVを算出できます。
サブスクリプション(SaaS)商材の計算式
SaaSのようなサブスクリプション型ビジネスでは、定額料金と解約率(チャーンレート)を使ってLTVを算出します。
LTV=平均購入単価×粗利率÷解約率
たとえば、月額1万円・粗利率80%・月次解約率5%の場合、
LTV=10,000円×80%÷5%=160,000円になります。
解約率は「一定期間に解約した顧客数÷期間開始時の顧客数」で求めます。
サブスクリプションでは、この解約率をいかに下げるかがLTV向上の最大のポイントです。
BtoB商材の計算式
BtoB取引では顧客ごとに収益率が異なるため、次の式でLTVを算出します。
LTV=1顧客の年間取引額×収益率×継続年数
たとえば、年間取引額500万円・収益率30%・取引期間5年の場合、
LTV=500万円×30%×5年=750万円になります。
BtoBビジネスは顧客数が限られる分、1社との関係を長く続けることがLTV向上につながります。
LTV向上で見込めるメリット
LTVを向上させることは、単に売上が増えるという表面的な効果だけでなく、経営基盤の強化や戦略的な意思決定の質を高めるなど、多面的なメリットをもたらします。
営業コストを軽減できる
「1:5の法則」が示すように、新規顧客の獲得には既存顧客の維持よりも5倍のコストがかかります。一方、既存顧客にはすでに信頼関係があるため、少ないコストでリピートやアップセルを促せます。
LTVを高める施策に取り組むことで、新規獲得に依存せず効率的な営業活動が可能になります。結果として、営業コストを抑えながら、浮いた資金を商品開発やサービス向上に活用できます。
収益を安定化させられる
新規顧客の獲得は、広告効果や市場動向などの外部要因に左右されやすく、収益が変動しやすい傾向があります。一方で、既存顧客からの継続的な収益は予測が立てやすく、経営の安定につながります。
LTVを高めることで、長期的に安定した収益基盤を築くことが可能です。
安定した売上は資金計画の精度を高めるだけでなく、金融機関からの融資や投資家からの評価向上にもつながります。
とくにサブスクリプション型ビジネスにおいては、この「収益の安定性」が企業成長を支える大きな強みとなります。
優良顧客の傾向を分析できる
LTVを顧客層ごとに分析することで、高いLTVを生み出す“優良顧客”の特徴を明確に把握できます。たとえば「40代女性でSNS広告経由の顧客が特にLTVが高い」といった傾向を掴めば、ターゲット設定や広告予算の最適化が可能になります。
さらに、高LTV顧客の購買頻度や利用パターンを深掘りすることで、ほかの顧客を優良顧客へと育成するための具体的な施策も導き出せます。
このように、LTV分析はデータに基づいた戦略的マーケティングを実現する重要な手段です。
経営の健全性を高められる
LTVと顧客獲得コスト(CAC)の関係は、事業の健全性を判断する重要な指標です。
LTVがCACを下回ると、顧客を獲得するほど赤字が増える構造になりますが、逆にLTVが大きく上回れば投資による成長が見込めます。
ユニットエコノミクスでは「LTV÷CAC」が3倍以上であることが健全な状態とされます。
つまり、1人の顧客を獲得するコストの3倍以上の利益を得られていれば、持続的な成長が可能です。
LTVを高めることは、このバランスを改善し、収益性と拡張性の両立を実現することにつながります。
LTVを向上させるためのポイント
LTVは複数の要素で成り立っており、それぞれを少しずつ改善することで全体の数値を高めることができます。
ここでは、定期通販事業で実践しやすい12の施策を、5つのカテゴリーに分けて紹介します。
1:購入単価を上げる
顧客一人あたりの購入単価を上げることができれば、購買頻度や継続期間が変わらなくても、LTVを直接的に高めることができます。
商品単価を上げる
商品の価格を適正な水準に見直すことは、LTVを高める最も直接的な手段のひとつです。ただし、単なる値上げは顧客離れを招くリスクがあるため、慎重な対応が求められます。
価格改定を成功させるには、品質や安全性、製造プロセスへのこだわりなど、「価格に見合う価値」を丁寧に伝えることが重要です。また、品質向上やサービス改善といった「価値の向上」とセットで行うと、顧客の納得を得やすくなります。
既存顧客に対しては、改定の理由を明確に説明し、段階的な価格変更や猶予期間の設定など、信頼関係を損なわない配慮を行うことが大切です。
アップセルを行う
アップセルとは、顧客が検討・購入している商品よりも上位プランや高価格帯の商品を提案する手法です。たとえば定期通販であれば、通常プランから大容量セットやプレミアムプランへの切り替えを促す施策がこれにあたります。
アップセルを効果的に行うには、顧客がすでに商品の価値を実感しているタイミングで提案することが重要です。
CRMツールなどで購入履歴や利用状況を把握し、購入回数の多い顧客やリピート率の高い顧客に対してパーソナライズした提案を行うことで、アップセルの成功率を高められます。
クロスセルを行う
クロスセルとは、購入した商品に関連する別の商品を提案し、購入単価を高める手法です。
たとえば、スキンケア商品を購入した顧客に同ブランドのサプリメントを紹介したり、コーヒーの定期便を利用している顧客にお菓子や抽出器具を提案したりするケースが挙げられます。
重要なのは、顧客にとって「本当に価値のある商品」を提案することです。
購買履歴や行動データを活用し「この商品を購入した方は、こちらも利用しています」といった自然なレコメンドを行うと効果的です。
ECサイトでは、商品ページや購入完了画面、メール配信など複数の接点でクロスセルを実施することで、より高い成果が期待できます。
2:購入頻度を増やす
同じ顧客により頻繁に購入してもらうことができれば、継続期間が同じでもLTVは向上します。
購入頻度に応じた付加価値を提供する
購入回数に応じてポイントが貯まる、特典がもらえるなどの仕組みは、顧客の購買意欲を高める効果があります。たとえば「10回購入で次回20%オフ」「累計購入額に応じて会員ランクが上がり、限定商品を優先購入できる」などの施策です。
また、配送サイクルを柔軟に調整できる仕組みを設けるのも有効です。
2か月に1回から1か月に1回へ変更できるオプションなど、利便性を高める工夫が購入頻度の向上につながります。
新商品やマイナーチェンジのサイクルを早める
同じ商品が続くと顧客の関心が薄れ、購入頻度が下がるおそれがあります。
定期的に新商品を投入したり、既存商品の改良や限定バージョンを発売したりすることで、購買意欲を維持できます。
たとえば、季節限定フレーバーを加える、数量限定の特別版を出すなど「今回は新商品も試してみよう」と思わせる工夫が効果的です。
さらに、顧客の意見を反映したリニューアルを行うことで、信頼感とブランドへの愛着を高められます。
3:契約期間を伸ばす(解約率を下げる)
顧客との取引期間が長くなるほど、LTVは大きくなります。解約率を下げ、継続率を高めることは、LTV向上の核心的な施策です。
定期購入やサブスクリプションを導入する
都度購入よりも定期購入のほうが継続率は高く、購入手続きの手間を省けるため「買い忘れ」による離脱を防げます。
定期購入を促すには、初回購入時にメリットを明確に伝えることが大切です。
「毎回10%オフ」「送料無料」「限定特典付き」など、魅力的な特典を提示すると移行が進みやすくなります。
また、解約を防ぐ仕組みも有効です。
解約画面で特別割引を提示したり、理由を聞いて柔軟に対応したりすることで、解約率を下げることができます。
顧客ロイヤルティを高める
顧客ロイヤルティとは、企業やブランドに対する信頼や愛着を指します。
ロイヤルティが高い顧客は、多少の価格差があっても他社に乗り換えず、長く継続して購入してくれる傾向があります。
これを高めるには、品質の維持に加えて、顧客との丁寧なコミュニケーションが欠かせません。購入後のフォローメールで活用方法を伝えたり、誕生日クーポンや感謝特典を贈ったりすることで、特別感を演出できます。
さらに、ブランドの理念や開発の背景を伝えることで、共感が生まれ、より強いロイヤルティを育てられます。
適切なタイミングで顧客にアプローチする
顧客の状況やニーズに合わせて最適なタイミングで連絡を取ることは、解約を防ぎ継続率を高めるうえで欠かせません。
たとえば、商品の使用期限が近づいた際にリマインドメールを送る、購入後に使用感をヒアリングする、解約が増えやすいタイミングで特別フォローを行うなどの施策が効果的です。
CRMやMAツールを活用すれば、行動データに基づいて自動で最適な時期にメッセージを配信できます。反応率の高い曜日や時間帯を分析し、より効果的なコミュニケーションを実現しましょう。
幅広い決済手段を用意する
顧客がスムーズに購入し継続できるよう、複数の決済手段を用意することが大切です。
ECではクレジットカード決済が主流ですが、個人情報の入力に不安を感じる人やカードを持たない人もいます。
そのため、コンビニ後払い・QRコード・キャリア決済など多様な方法をそろえることで、より多くの顧客に対応できます。とくに後払い決済は、商品到着後に支払える安心感から初回購入率の向上に効果的です。
一方、定期通販では、クレジットカード決済のほうが継続率が高い傾向にあります。
初回は後払いでハードルを下げ、満足度が高まった段階でクレカ決済へ誘導することで、新規獲得と継続率向上の両立が可能になります。
4:顧客獲得・維持のコストを下げる
購入単価や頻度、継続期間を改善しても、顧客獲得や維持にかかるコストが増大してしまえば、LTVの向上効果は相殺されてしまいます。コスト効率を高めることも、LTV向上の重要な要素です。
ツールを用いて業務効率化を図る
顧客管理やマーケティングにかかるコストを抑えるには、CRMやMAツールの活用が効果的です。
CRMを導入すれば、顧客情報を一元管理でき、購入履歴や問い合わせ内容をすぐに確認できます。これにより、対応品質の向上と業務の効率化を同時に実現できます。
MAツールでは、行動データに応じたメール配信やスコアリングを自動化できます。
限られた人員でも多くの顧客に最適な対応ができるため、人件費を抑えつつ顧客満足度を高められます。
ターゲットと施策を絞る
すべての顧客に同じリソースをかけるのではなく、LTVの高い層や将来的に高くなる見込みのある層に注力することが効果的です。
まずは既存顧客データを分析し、高LTV顧客の特徴を明確にします。
年齢や購入傾向、流入経路などを把握し、その結果をもとに新規獲得のターゲティングを最適化しましょう。
高LTV層に広告予算を集中させることで、無駄なコストを抑えながら費用対効果の高い集客が可能になります。
また、解約リスクが高い顧客を重点的にフォローするなど、リソース配分にメリハリをつけることも重要です。
5:顧客数を増やす
LTVを高めるだけでなく、将来的に優良顧客となり得る新規顧客を継続的に獲得することも重要です。既存顧客を維持していても、ライフスタイルの変化や購買行動の移り変わりによって、一定の自然減は避けられません。
そのため、高LTV顧客の分析結果をもとに、価値の高い層を狙った新規獲得施策を行いましょう。
さらに、紹介プログラムを導入すれば、満足度の高い既存顧客を通じて、質の高い新規顧客を低コストで獲得できます。
紹介者と被紹介者の双方に特典を設けることで、参加意欲を高め、プログラム全体の効果を最大化できます。
まとめ
LTVの向上は、定期通販ビジネスを安定的に成長させるうえで欠かせない要素です。 新規顧客の獲得コストが年々高騰する中、既存顧客との関係を深め、長期的に収益を積み上げていくことが、今後の競争力を左右します。
なかでも注目すべき施策が「決済手段の最適化」です。後払いによって初回購入率(コンバージョン)を高め、顧客が商品に満足した段階でクレジットカード決済へ移行することで、LTVの最大化を実現できます。
LTV向上の第一歩は、決済体験の改善から始まるといっても過言ではありません。
株式会社SCOREが提供する「スコア後払い」は、与信審査から代金回収までを一括で対応し、リスクと手間を大幅に軽減いたします。コンビニ後払いによる初回購入率UPと、クレジットカードによる継続率UPを両立したい方は、ぜひ「スコア後払い」の導入をご検討ください。
スコア後払いは、全国のコンビニや郵便局、アプリでの支払いが可能です。申し込みから最短5営業日で導入できます。お困りの際にはぜひお問い合わせください。
業務の効率化を図り、なおかつ安心感が得られる後払いサービスを探しているならば、スコア後払いを検討してみてはいかがでしょうか。 →SCOREへの後払いの導入相談はこちらから